TBS系全国ネットTV番組「林先生の初耳学!」の2021年1月10日放送回で、一夜にして数千万円を稼ぐ生きる伝説と呼ばれた現代ホスト界の帝王、ROLANDさんがゲスト出演されました。
普段TV番組を見る事がほとんど無い私、にこる(@choco2col)ですが、今回この番組を偶然視聴したにもかかわらず、ゲストのROLANDさんや進行役の林先生の言葉が、過去の夢を叶えられなかった自分や、幼児教育に興味がある今の自分に突き刺さりました。
お互いの方向性や考え方など、全然違うお二人の言葉はそれぞれに意味と理由があり、この先の人生で悩むことがあったらぜひ耳を傾けて欲しい!と心から思えたので、番組をご覧になった方や、見逃してしまった方にもできるだけ理解しやすいように記録しておきたいと思います。
そのため、会話の内容など一文字一句同じ言いまわしで記録しているわけではありませんのでご了承ください。

MOKUJI
番組の意向・序章
過激な発言で時には反感を買いながらもその姿勢が注目され、自身が書いた著書も売れて一躍スターになったローランドさんですが、2020年、彼にとって最も話題となったのが経営するホストクラブの閉店でした。
コロナ過で誰もが苦しい時代に苦渋の決断をし、堂々と前向きに生きるローランドさんにポジティブに生き抜くヒントを問う。

原点:夢を諦めた高校時代
物心ついた幼少期からサッカーをしていた
勉強も青春も恋愛も、全て犠牲にして打ち込んでいたが、その背景には自分がプロになれる自信があったからだという。
中学時代にJリーグの下部組織チームに所属していたローランドは、高校は特待生でサッカーの名門帝京高校に入学。
サッカー漬けの毎日を送っていた中、2010年高3の秋に全国大会予選の決勝で敗れて引退。プロになるという夢を叶えられなかった。
プロになった人たちと自分と何が決定的に違った?
純粋に一個だけ言うとしたら「才能」だなと。
ローランドはこの時、自分自身が考えうる全ての努力をしたという。
全力で頑張らなかったら、なれなかった原因すらわからない。24時間、365日、10年以上、真剣に打ち込んだ。これでなれないんだとしたら、ただ向いていなかった。

夢を叶えられなくてもすぐに次のステップにいけた理由
なぜすぐに次のステップに行けたのか、ローランドは自身の経験を通して分かりやすい比喩表現で語っている。
- お化けと一緒で未練があるから悪霊となって出てくる。やりきったら天国にいけるのと同じ。
- 全力でやらなかったら、叶わなかった時に、もう夢とも言えない夢をだらだら追いかけることになる。
- 全力でやることの意味は、もちろん成功する可能性が高まるということもあるけど、ダメだった時でも成仏できる、次のステップに行こうと思える、それが全力でやることの意味なんじゃないかと思う。
全力で頑張れば未練なく次のステップに進むことが出来る。

転機:大学は入学式で自主退学
人の決めた人生は歩めない
高校卒業後は先生や両親に勧められたこともあり、大学に進学することを一度は決断するも入学から数日後には自主退学してしまう。
本人の著書によると「大学の入学式の日、ここは俺の居場所じゃない、そう実感した。俺は人の決めた人生は歩めない。」と記してある。
この行動について、進行役の林修はローランドにこう問いかける。
良い大学に入ってそこで頑張る生徒をたくさん見ているが、そういった選択をスパッとやめられた。良い大学に入って普通に社会に出るルートをどう思う?
この質問に対してローランドは以下のように回答している。
それは成田に行きたくて行ってるというよりも、ニューヨークに行くために必然的に行かなくてはいけない場所であって、行き先が決まっていないのに空港にいる人は一人もいない。
大学という空港には行き先も決まっていない、飛行機のチケットもパスポートも持っていない人が大勢いる、そこは疑問を感じる部分。
大学に行けば幸せになれるというようなプロパガンダはちょっと違うと思う。
プロパガンダとは?
プロパガンダ(propaganda)とは、特定の思想によって個人や集団に影響を与え、その行動を意図した方向へ仕向けようとする宣伝活動の総称です。特に、政治的意図をもつ宣伝活動をさすことが多いですが、ある決まった考えや思想・主義あるいは宗教的教義などを、一方的に喧伝(けんでん)するようなものや、刷り込もうとするような宣伝活動などをさします。
文章引用:WORD-WISE WEB 三省堂
ローランドの発言通り、街中の現役大学生にインタビューするシーンでは、以下のような回答が続いた。
現役大学生のコメント
- 大学に行くのが世の中のステータスになっている
- とりあえず大学に入っておけば、と考える人は多い
- 大学名だけほしい

ポジティブに生き抜くヒント【2】
大学は目的もなく行く場所ではない。

自分は大学に行かなくても上手くいくという自信はあった?
自負はあった。できるだろうという、ちょっと素敵な勘違いだったのかもしれない。
人生を変えるのに必要なことって、いろんなことがあるかもしれないけど「ちょっと素敵な勘違い」が出来るかどうかというのも結構大きいところだと思っている。
林修が思う、大学の位置付けや良い大学に行くことの定義は?
大学は目的もなく行く場所ではないと語るローランドが、これまで予備校講師として長年教育の現場に立っていた林修に、逆に大学の位置付けや良い大学に行くことの定義を問いました。
周りをみると、いわゆる良い大学に行っている人たちは、そんなに大したことない。…という事を授業で(若い世代に)伝えます。
特にこれからは大変な時代で、今まで以上に良い大学を出たことの意義が下がるので、入ったらすぐに走り出さないとダメだよ、という話はする。

それでも目的もなく大学に行く人もいるわけじゃないですか?
高校までに見える世界はあまりにも狭い。
結局何かしたいと思うのは、どういう情報を得るのかというのと関数の問題。
将来がわからないまま、とりあえず大学に行ってみるという選択というのは、特に地方にいればより世界は狭いですから、それは仕方がないという考えなんです。

ピンボールみたいに弾かれているうちに、なんか良いボーナスをゲットしている…という生き方というのも一方ではあって、その最たるものが自分だと言う林修は、(ピンボールのピンを)ピンと弾いた先に「今でしょ!」ボーナスにガチャンと当たったと語る。
なぜ勉強しないといけない?と問われたらどう答える?
結婚願望は全くないと語るローランドだが、もし自分の子どもが生まれた時に「何で父さん、勉強しないといけない?」と問われたら、俺はなんて答えるんだろう?と想像したことがあるという。
「何で勉強しないといけない?」と聞かれたら、なんて答えるんですか?
「勉強しないといけない?」と聞く人は勉強しなくていいと思っている。
逆に、なんでサッカーをされていたんですか?
好きだから。
ローランドがこう回答するのを最初から解っていたかのように質問した林修は続けてこう語る。
やっていて楽しい、だからこうなった。
やってて楽しくないなら続かないし、やらなくていいと思っている。
勉強が楽しいと思うかは、実は結構環境が大きい。
親が楽しそうに本を読んでいたり、楽しそうに問題やパズルを解いたりしている姿を見ていて子どもが真似をする。
勉強が好きという想いを抱くかどうかは、親の責任だと思っています。

勉強を無理強いする教育には疑問を感じている?
林修のこの発言に対してローランドは、無理強いする事に意味がないと思っていると語り、経営者になってから特に実感していることだという。
- (従業員に対して)売り上げを上げろと言うよりも、カッコいいスポーツカーの助手席に乗せて「この車カッコいいだろ?いつか買いたいだろ?」と言った時の方が良い顔で出勤してきたりする。
- やらせるというよりも、やりたいと思わせることに、もしかしたら日本の教育というのは問題点としてあるのかもしれない。
やらせるというよりも、やりたいと思わせることが大事

俺か俺以外かの真相
メディアに対してのブランディングを絶えず研究している

林修はインタビューする前に著書を読み、ローランド自身のブランディングに対して絶えず研究し続けていることを例に挙げ、特にブランディングで意識していることは何か?と問う。
知ってもらう事が大事で、無名な奴に力はないと思っていた。
知ってもらうために過激な発言をしたり、トゲのある発言をしていたが自分本位ではなく、知ってもらうためにはしょうがないなというブランディングをしていた。
正直お金に興味はないが、こういった派手な生活していますよ、とか何千万売り上げましたとか、僕からしたら喋っててもくだらないなと思っていた。
それがメディアからしたらアイコニックになるというか、アイキャッチになるワードにもなるということを意識してやっていた。

現在ローランドは、もう知ってもらう過程は少し終わってきたのかな?と語る上で、現時点でのブランディングとして意識しているのは、素のままの自分を知ってもらうことだと話す。
そういった過程を経ての今がある。
ポジティブに生き抜くヒント【4】
過激な発言は自分を知ってもらうため
誰にも知られていない自分では何を言っても響かない。

SNSに対する想いと遮断力について
自分を知ってもらうために過激な発言をし、その過程を経ての現状について、林修はローランドに対し「そこはちょっと通じるものがある」と賛同する。
その頃(まだ知名度がさほど無かった頃)は、ちょっと尖ったことを言うと賛同者がたくさん出ていた。
ところが、ある時期を越えると強い発言に対してのアンチが多くなるということを実感した。

そう語る林修は、「一日はエゴサに始まり、エゴサで終わる。」と言い切るほど、ネット上の情報を日々閲覧していると言う。
逆にSNSを全く見ないと言うローランドは、林修のように強いタイプの人間ではないので、良い事でも悪い事でも何を書かれていても気にしてしまうと語る。
大人たちは「聞く耳を持て」と言うけど、僕はこの時代だからこそ「聞かない耳を持て」と言いたい。
聞かないからこそ出来ることだったりとか、メディアで何を言われているかなどをいちいち気にしていたら、右向け右のつまらない人間になっていく。僕はそれが怖くてSNSなどは見ないようにしている。
林修は、ローランドのその意識を遮断力と呼んでいる。
遮断力が強くても、必要な情報だけは的確に吸収していると仮定する林修に、この時代を生きていると、知らないといけない情報は嫌でも耳に入ってくると語るローランド。
知ろうとしなくてもいずれ知ると思ったら、調べる時間も無駄。
知らなくてもいい事まで知るくらいなら、おせっかいな人がいずれ知らせてくれるから、今の便利な世の中で自分から情報に歩み寄る必要はないと思っている。

ローランドがこう語る一方で、情報を遮断しないという林修の考えには理由があった。
林修が情報を遮断しない理由
相手が思いやりで言わなくてもそれは結局言われているのと一緒だということ。
逆に事実じゃない事が書かれれば、そこには何らかの想いがあると。
その想いを知ることが自分にとってプラスになるという考え方なので、僕は遮断しない。

この情報過多の時代だからこそ、遮断して上手くいくタイプの人もいれば、上手に吸収するタイプの人間もいる、ということ。
ポジティブに生き抜くヒント【5】
なんとなく(SNSを)見て、なんとなく病んでいる人は、どっちかに美学を持って欲しい。
そうすることによって、心の負担を減らすことが出来るかもしれない。

生涯をかけて叶えたい目標
知ってもらう時期は終わったというローランドは今後何をしていこうとしているのか?
実業家としてやっているのは、利益ではなく自分がやりたいことが全てなので「コロナが収まったらこの事業を(やりたい)」というのは無く、自分がやりたいことをずっとやり続けられるのが理想の人生だと語るローランド。
具体的にやりたいと思う事業はあるんですか?
チャンピオンズリーグという欧州最強のサッカークラブを決める大会で、選手が入場する時に流れるアンセムを聴いた時の心の高まり具合は、他のどの素敵な瞬間よりも一番興奮できるということを、最近になって改めてわかった。
選手としては無理かもしれないが、サッカークラブを経営するということはやりたい。
日本にとどまらず世界へ出ていくこともある?
夢は言わないと叶わないと思っているので、まず目指すところからはじまる。
宣言したからにはやりたい。

自分のやりたいことをずっとやり続けていく?
自分はそういう人生でしたし、今後もそうありたい。
終章
自分のやりたいことを今後もずっとやり続けていきたいと、ポジティブに語るローランドに対し「自分のやりたいことにこだわる感覚がない」と、一見ネガティブのようにも聞こえる発言をする林修にローランドは問う。
人生でやりたくないことも出来る?
今の現代社会、自身が本来やりたくないことをして生活している人も大勢いる中で、なぜそれをやりたいと思ったかの原点を掘り下げてみると、偶然知った情報や環境との関係でやりたいと思う事が多いと林修は考え、過去の東大入試問題を例に挙げて自分の想いを語っている。
東大現代文2011年問題の一節
人間の「何かしたい」は環境や情報との関わりの中で偶発的に出るということがある、というのが僕の考え。

実際には自分のやりたい事にこだわって上手くいっている人はいるが、その一方で、やりたい事にこだわって結果が出ずに苦しんでいる人もいる。林修は最後にローランドへ向けて、そんな方たちにどんなアドバイスをしますか?と問いかける。
成功する事が幸せと思う人もいれば、やりたいことが出来ることが幸せと思う人もいる。
極論、やりたい事で成功するのが一番いいんだと思うんですけど、そういう若者(結果が出ずに苦しんでいる人)には、自分の心に問いただせと言っている。
お前は成功することが幸せと思うのか、やりたいことが出来る現状が幸せなのか、どっちなのか心に聞いてみろと。
その時に成功したい!と心の声が言っていたら、多少自分のやり方を曲げてでも成功に歩み寄る姿勢は大事。
成功はしなくてもやりたい事が出来る事こそが幸せだと心の声が言ってきたら、今のままを貫けばいい。

自分の心の声が一番素直な自分の想いなんだと、ローランドは語る。
ポジティブに生き抜くヒント【6】
将来が不安なら自分の心に問いただす
成功が幸せか?やりたい事をやるのが幸せか?

編集後記
普段テレビを見る機会がほとんどない私が、偶然視聴したテレビ番組の内容を記事にまでおこして記録したいと思ったのはごく稀な出来事でした。
今回記録するにあたり放送回を繰り返し見ていて思ったのは、それぞれ生き方や考え方が全く異なるお二人でも、それぞれの意見に共感し納得はできるものの、言葉の言い回しや文章の一語一句、表現の仕方など細かい部分をみていると、やっぱりローランドさんはお若いな、まだまだこの先経験の伸びしろがあるんだろうな、と思わずにはいられませんでした。
一方の林先生は、ローランドさんより人生を長く生きている分、そして現代文の講師でもあるので、余計な言葉は使わず的確に自分の想いをスムーズに伝えられる巧みさを感じました。
そしてお若いローランドさんでも、対談中何度も「そうなんですね」という言葉を使っていたのがとても印象的でした。
世間的には嫌煙されがちな「そうなんですね」という言葉ですが、相手の言い分に耳を傾け、それを否定せずに受け入れる姿勢を感じられて私は好きです。
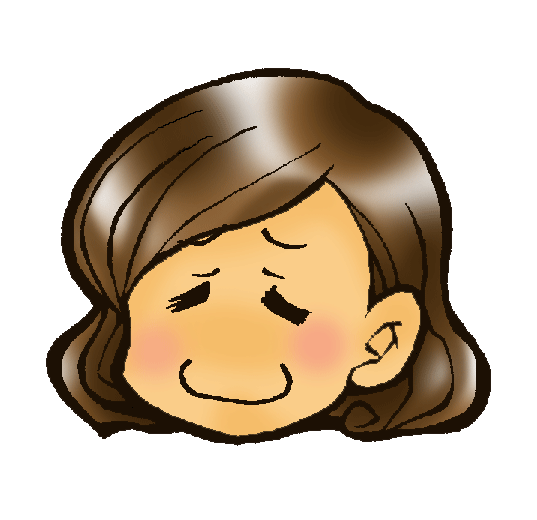 にこる
にこる
実は林先生とローランドさんの対談は、次週後編が放送されるそうです。
前編だけで納得の内容だったので、後編を記事にするつもりは今のところありませんが、今回以上の内容であればもしかしたら次回も文字に起こすかもしれません。
機会がありましたら、また!
にこる(@choco2col)でした!



